2025.08.29
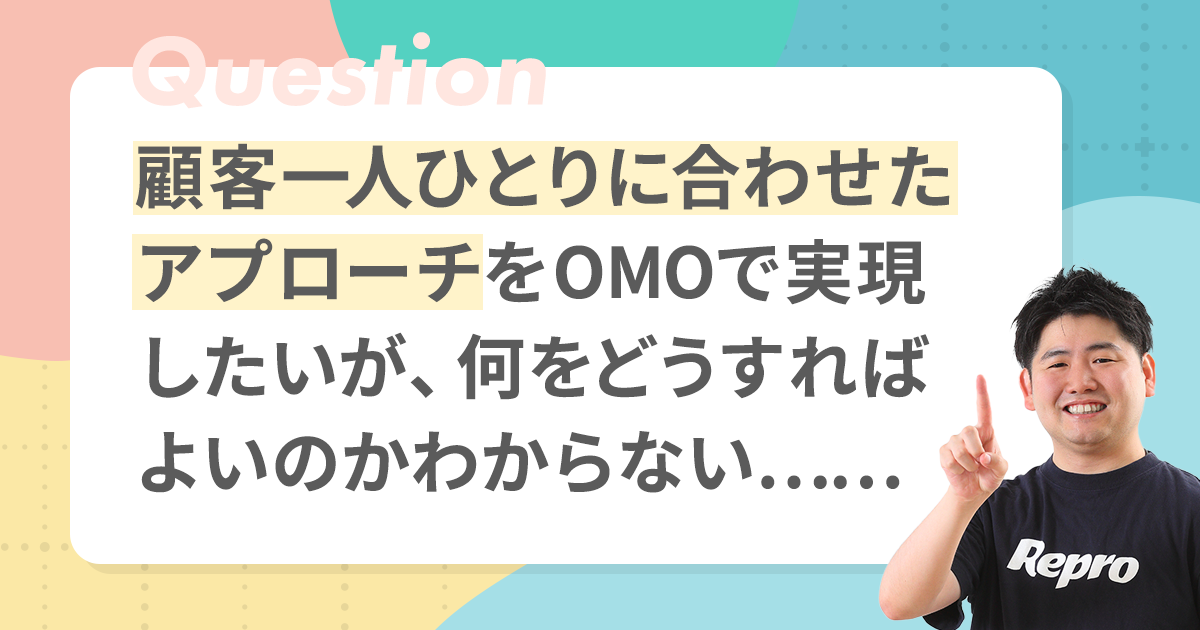

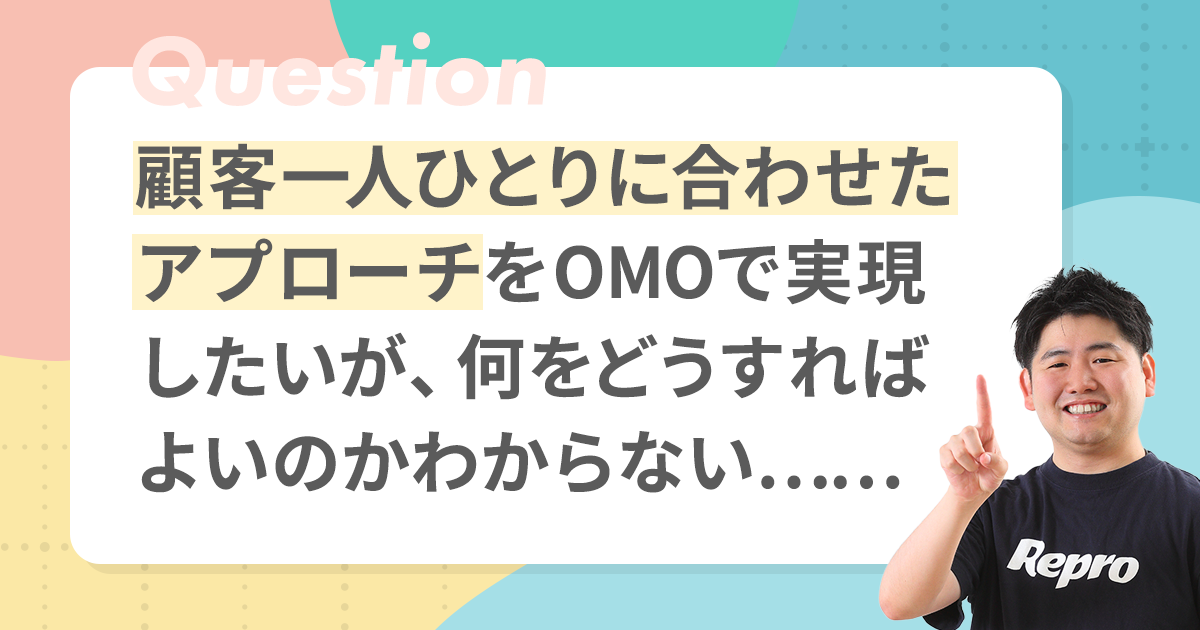
【今回のご相談】
リアル店舗とECアプリのふたつのチャネルを活用し、弊社でもいわゆるOMO戦略を進めています。私自身データ分析に強みがあると自負しており、特にアプリを通してお客様のニーズや行動はうまく把握できるようになりました。
そうなると、色々なところで耳にする「1to1コミュニケーション」のようなことができるのではないか、と考えている今日この頃です。残念ながら考えているだけで、具体的な施策は始められていません。セミナーなどで話を聞いても、なんとなくふわっとしていて、何をすればよいかもわからずに二の足を踏んでいる状況で、店舗とアプリでは顧客体験が分断されているのが実情です。
社内からもアイデアは出てくるのですが、いまいち方向性が定まらず……いったい何から手を付ければよいのでしょうか?(リテール・アプリマーケティング担当、30代男性)
近年、消費者はECや店舗、SNSなど、複数のチャネルを行き来しながら購買行動を完結させるようになりました。こうした行動に対応するため、チャネル横断で一貫した顧客体験の設計を試みる企業が増えています。
特に注目されているのが“1to1コミュニケーション”です。顧客一人ひとりに対して、最適なタイミング・手段・内容で情報やサービスを届けるこのアプローチは、LTV(顧客生涯価値)の最大化やロイヤルカスタマーの育成において欠かせないものとなりつつあります。
一方、「やるべきことは理解しているものの、どう実行すればいいのかがわからない」といったお悩みを抱える担当者は少なくありません。今回は、OMO文脈における1to1コミュニケーションをテーマに、実践に向けた課題と解決のヒントを紹介します。
「顧客一人ひとりに合わせたアプローチを実現したい」。そう考える企業は多いものの、継続的に1to1コミュニケーションを実行できている例は決して多くありません。
OMOが進んだことで、顧客の行動やニーズをオンライン・オフライン問わず細かく把握できるようになりました。しかしその一方で、店舗・アプリ・ECなど複数の接点が分断され、ツールは導入されていても活用方法が現場に共有されていないなど、施策の実行に“見えづらい壁”が立ちはだかるケースも少なくありません。
アプリで取得した行動データを活用したいマーケティング部門と、それを実際に活かすべき店舗スタッフとの間に生じる認識のズレ。「個別対応はしたいけれど、時間的にも端末操作的にも難しい」といった店舗スタッフの本音。こうした“運用の温度差”は、設計段階で想定しづらく、実行段階で浮かび上がる課題のひとつです。
このように、1to1コミュニケーションは理論としては広く語られていても、実際に成果を出すためには、現場と仕組みをつなぐ運用設計や組織連携まで踏み込んだ取り組みが求められます。
1to1コミュニケーションを実現するには、オンライン・オフラインのチャネルを組み合わせた体験の設計が欠かせません。
とはいえ、いきなり理想の施策を描くのは簡単ではないもの。ここでは、実際の現場で取り組まれている代表的なパターンを基に、具体的な施策のイメージを紹介します。
顧客行動データを活用した施策としては、購入直後にお礼や使い方の案内を送信し、顧客満足度や再購入意欲を高める取り組みがまず挙げられます。
スーツを購入したお客様に対して、アプリ上でそのスーツに合わせやすいシャツやネクタイをおすすめする。アプリで配付したクーポンが未使用の場合にリマインドを送る。品切れによって店舗での商品購入がかなわなかったお客様に対して再入荷情報や近隣店舗の在庫状況を個別通知する。
このように、顧客にとって「求めていた情報が最適な形で届く」体験が、満足度とLTVの向上を後押しするのです。

さらにもう一歩踏み込むなら、「自分が気づいていなかったニーズに先回りしてくれる」体験も、1to1ならではの魅力です。たとえば、あるカテゴリを何度も閲覧しているユーザーに対して、該当商品の特集ページや相性のよい関連アイテムを提案することで、「これも欲しかった」と感じてもらえる“発見のきっかけ”をつくることができます。
単に情報を届けるだけでなく、顧客の期待を少し超える。そんな設計が、満足を超えて“記憶に残る体験”へとつながっていきます。
購買頻度や金額に応じて会員ランクを設定し、ランクアップ時に限定クーポンや先行情報を提供する施策も有効です。
さらに、ランクによって表示コンテンツや提案内容を切り替えることで、「自分に合わせた対応をしてくれている」と顧客が実感できる体験をつくることができます。
こうした“特別扱い”が、継続利用や来店の動機につながっていきます。

アプリで取得した行動データをもとに、LINEやメールなど他チャネルと連携した個別配信を行うと、顧客体験に一貫性が生まれます。

たとえば、カートに商品を残しているユーザーにプッシュ通知で リマインドを送り、その後の閲覧状況に応じてアプリでも別のメッセージを表示する、といったように接点ごとの役割をつなぐことで、“ひとつながりの体験”を実現できます。
また、プッシュ通知をオフにしているユーザーには、LINEやメールでのフォローを設計するなど、情報接触の機会を補完する工夫も有効です。
こうした体験を成立させるには、チャネルごとの特性や接触頻度を理解したうえで、重複や過剰接触を防ぐ設計も重要です。「どのチャネルで、どんな役割を持たせるか」を整理し、全体設計に落とし込んでいくことが、無理のない継続運用のカギになります。
施策のアイデアだけでは、1to1コミュニケーションはうまく機能しません。ポイントとなるのは、施策を「実行し続けられる仕組み」に落とし込むこと。
最後に、体験設計や運用体制を構築するうえで、あらかじめ意識しておきたいポイントを紹介します。
まず大切なのは、「どんな体験を届けたいのか」という顧客視点のゴールを明確にすることです。
そのうえでKPIツリーを設計し、店舗とデジタル部門の共通言語として活用すれば、組織横断で施策を進めやすくなります。
KPIツリーを作る最大のメリットは、「今やっている施策が、どの体験の実現につながっているのか」を明確にできる点にあります。抽象的になりがちな目的を、現場が理解できる言葉に“翻訳”すれば、現場と企画のズレを最小限に抑えることができます。
【関連記事】OMO施策を成功に導くために「KPIツリー」を作ろう(Repro Journal)
データ活用の前提となるのは、アプリのインストールや会員登録といった初期接点の獲得です。たとえば、店舗でのインストール促進では、「このアプリでこんな特典があります」と来店時に案内するだけでも、ダウンロード率が大きく変わります。
さらに、2度目の来店・購入につなげるために、初回購入直後にクーポンを配信したり、ポイントを即時に付与したりと、“次の行動”を後押しする仕掛けも有効です。
こうした仕組みと現場の導線をあらかじめ設計しておくことで、データの蓄積と活用が自然に進み、施策全体の成果にもつながっていきます。
【関連記事】OMO施策の成果を分ける“店舗での体験設計”とは?(Repro Journal)
本記事でご紹介したように、OMOにおける1to1コミュニケーションを成功に導くには、「どんな体験を届けたいか」という目的から出発し、チャネル連携・KPI設計・運用までを一貫して考えることが重要です。
顧客にとって“ちょうどいい”タイミングで、ちょうどいい方法でアプローチできるようになることで、信頼関係やブランドへの親しみが育まれ、それがLTV向上やリピート率改善、再来店の促進といった成果につながっていきます。
OMO施策を推進するうえで、「ツールを導入したのに活用しきれない」「部門間で足並みがそろわない」といった課題に直面している方も多いのではないでしょうか。
Reproでは、こうしたOMO時代の体験設計や1to1施策の立ち上げ・運用支援を行っています。
「何から始めればいいのかわからない」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。
▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。