2025.07.10
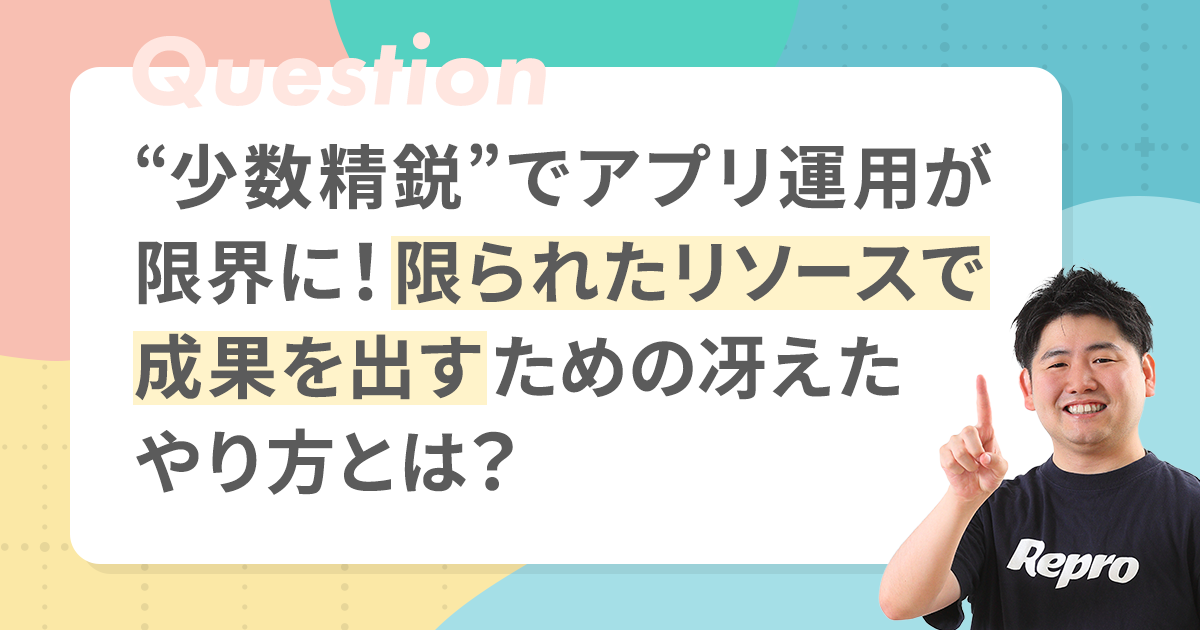

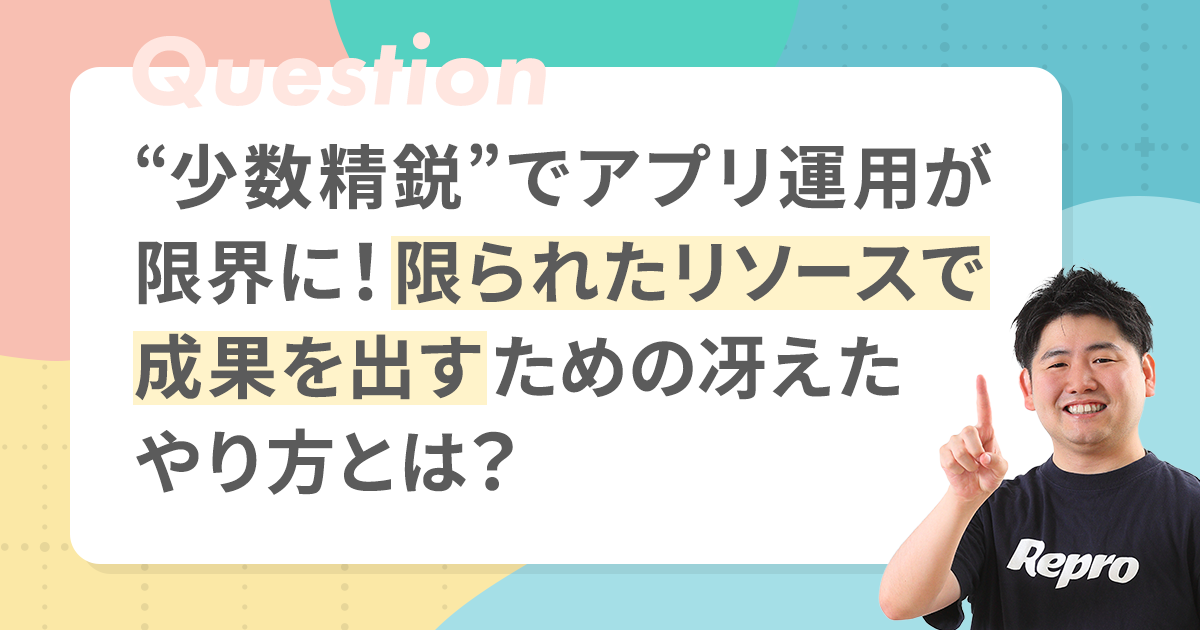
【今回のご相談】
私の会社ではECを中心にいくつかの事業を行っており、そのひとつとしてアプリを運用しています。アプリ専任の担当者は私ひとりで、あとは兼務スタッフが2~3人の“少数精鋭”……と言えば聞こえはよいものの、はっきり言ってしまえば単純に手が足りていない状況です。
アプリ自体に改善が必要なことはわかっているのですが、何から手を付ければよいのか、知見も時間もなく……。今すぐ社内リソースを増やすことはできず、しかし会社からは結果を出すことを求められています。
そこでお聞きしたいのですが、仮に外部の力を借りるとすれば、何をお願いすればよいのでしょうか。目の前のことだけで精いっぱいで、今はそれすらも思いつきません。(ECアプリ運用、30代女性)
アプリをリリースしたものの、改善施策にまで手が回らず、運用が滞ってしまう。そんな悩みを抱えているチームは決して少なくありません。たとえばECアプリの運用では、日々のチューニングやユーザー対応が求められる一方で、運用を担うのは少人数の兼任チームというケースも多く見られます。
では、限られたリソースで成果を出すためには、どこまでを自社で行い、どこから外部の力を借りるべきなのでしょうか?
今回は、実際の現場の課題と照らし合わせて、「内製すべき業務」と「外注すべき業務」の見極め方を整理します。リソース不足に悩むアプリ運用担当者の方は、ぜひご一読ください。
アプリを公開しても、改善に着手できないまま止まってしまう。そんな現場には、判断や実行の壁が存在しています。まずは、改善が始められない背景とリスクについて見ていきましょう。

たとえば、設計や開発を外部委託している企業では、「修正したい点があるものの、要件定義が社内でできず手が打てない」といった状況に陥るケースが少なくありません。
この背景には、設計変更や改善依頼に必要な「知識・スキル」や「リソース」の不足といった問題があります。また、利用しているツールや開発方式によっては、仕様上の制約から「やりたくてもできない」ケースもあり、より状況が複雑になっています。
なかには、アプリ運用の経験がないままトップダウンでプロジェクトが進行し、知見がない担当者に運用が丸投げされてしまうことも。そうした現場では「何が課題か」「どこから手をつけるべきか」を整理できず、結果として運用が動かないまま時間だけが過ぎてしまいます。
本来、アプリの運用で最も重要なのは、公開後にユーザーの離脱ポイントを見極め、対応策を打ち続けていく改善フェーズです。しかし、その“穴埋め”のための体制やノウハウがないまま放置されている現場も少なくありません。
改善が進まない状態が続くと、数字の悪化は見えても「なぜ悪いのか」「どう変えればいいのか」が判断しづらくなっていきます。
アプリ運用では、改善のための試行錯誤そのものが、ユーザー理解や成功パターンの発見につながる重要な活動です。ところが「打ち手を動かせない」状態では、そうした学びも蓄積されません。
その結果、「改善が止まる→原因も見えない→次の一手が打てない」という悪循環に陥ってしまうのです。
限られた人数・予算で成果を出すには、「何でも自社でやる」のではなく、どこに自社の力を割き、どこで外部の力を借りるかという任せ方の設計が鍵となります。
特に重要なのは、最終的に自社に知見がたまる設計になっているかどうかという視点。一時的に外部に任せる場合でも、社内にやり方や考え方が残るようにしておくことが大切です。長期的には、自社で再現できるかたちにしていくことで、運用の柔軟性や改善スピードも保ちやすくなります。
また、予算が限られている場合も、目先のコストだけでなく、「半年間プロに任せたらどこまで成果を出せるか」「その間に何を内製に移行できるか」を基準に判断することをおすすめします。
ここからは、どのような業務を内製するべきか、具体例や考え方をご紹介します。
ユーザーインタビュー、レビュー分析、定量調査など、顧客の声に触れ、顧客解像度を高める業務は社内で担うべき重要な領域です。ここを外注してしまうと、企業としての学びや次の手の打ち方が見えづらくなってしまいます。
アプリ運用の改善方針や戦略の精度は、ユーザー理解の深さに比例するもの。顧客の声に耳を傾け続けることで、自然と自社に「ユーザーが何を求めているのか」「改善に向けて何をするべきか」といった知見が自然に蓄積されていくことでしょう。
たとえば「プッシュ通知の文面」や「配信タイミングの調整」などは、ユーザーの反応を見ながら何度も試すことが前提の業務です。成果につながるまでには数十回単位のトライアンドエラーが必要になることも少なくありません。
このような業務は、戦略よりも“試行回数と早さ”が物を言うため、都度外部に依頼するのは効率的ではありません。
作業としての難易度は高くないため、インターンや業務委託など比較的ジュニアな人材で回せる体制を整えることで、施策の効果検証を着実に進めやすくなります。
UI文言の調整やボタン位置の変更といった小さな改修を社内で即時に反映できるかどうかは、運用スピードに直結する要素のひとつ。
こうした“軽微な手直し”は、外注するとコストやコミュニケーションの面で割に合わず、手を打つのが遅れがちです。
社内に開発リソースを完全に抱える必要はありませんが、「ここは自分たちで直せる」という最低限の機動力は、改善の継続性を保つうえで重要な要素といえます。
一方で、リソース確保や戦略・施策の精度向上といった観点から、外部への委託を検討したほうがよい業務もあります。
社内にアプリマーケティングの経験者がいない場合、あるいはスピードを重視したい局面では、プロである外部パートナーの活用が効果的です。
特に「何から手をつけていいかわからない」といった初期段階では、外部の知見を取り入れながら、戦略の型を整えていく進め方を選択するのが現実的です。
初期設計フェーズを外部と並走し、方針が定まった段階で自走に切り替えれば、スムーズに成果につながりやすくなるうえ、社内に知見も残りやすくなります。
広告運用において本当に重要なのは、「数値をどう読むか」「次の施策にどう活かすか」といった判断の部分です。
しかし実際の現場では、レポート作成や媒体ごとの数値確認、代理店とのやりとりなど、定型的な作業に多くの時間を取られてしまうケースも少なくありません。
こうした業務は外部に切り出すことで、配信結果の分析や次回のクリエイティブ設計など、運用の改善に直結する業務に時間を割けるようになります。
自社にアプリ開発に関する豊富な知見を持つメンバーが不在の場合、アプリのデータ設計・取得基盤の構築に外部リソースを活用するのがおすすめです。
アプリにおけるデータ計測の設計は、Webに比べて構造が複雑です。アプリ上のユーザー行動を正確に把握するには、画面単位・イベント単位での細かな設定が必要となるため、初期段階での要件定義には専門的な知見が求められるのです。
データを正しく取得できなければ、分析も改善もうまく機能しません。
そのため、計測設計やツール実装のような基盤づくりについては、最初からプロの力を借りたほうが後の運用効率と施策精度の向上につなげやすくなります。

自分だけが悩んでいるように感じられてしまう瞬間にも、実は多くの人が同じ壁にぶつかっているもの。正解のないアプリ運用に悩んだときこそ、頼りになるのが同じ課題を抱える仲間や実践知を持つプロの存在です。
アプリ運用を担当していると、正解が見えないなか、ひとり手探りで走り続けなければならない場面が少なくありません。特に少人数体制や兼任の現場では、「本当にこれでいいのか?」と不安を抱えたまま業務を進めている方も多いのではないでしょうか。
そんなときに力になるのが、同じ立場の人と課題や工夫をシェアできる“横のつながり”です。似たような悩みを抱える他社のリアルな声や実践知に触れることで、自分たちの状況を客観視できたり、次の一手を見つけるヒントを得られたりすることも。
Reproでは、アプリマーケターのための学び合い・支え合いのコミュニティ形成にも力を入れており、イベントやミートアップを通じて実践的な情報交換の場を提供しています。
⇒現在予定しているイベントの一覧はこちら
アプリ運用の初期フェーズでは、自社だけで答えを出そうとするよりも、客観的な視点や他社事例に触れるほうが、最短で成果につながるケースも少なくありません。
たとえば、ハンドメイドマーケットアプリ「minne byGMOペパボ」では、Reproの支援を通じてプッシュ通知からの流入が前年比189%にまで改善。単に施策の数を増やすのではなく、結果を見て即座に打ち手を切り替える高速なPDCA体制と、事業やユーザー特性に合わせた運用方針を一緒に考えられる関係性が、成果につながる大きな要因となりました。
自社に合った運用の“型”を見つけるうえでも、専門家の伴走は大きな武器になります。
▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼
Reproでは、アプリ運用のお悩み相談を随時受け付けています。ぜひ気軽にお問い合わせください!

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。