2025.09.10
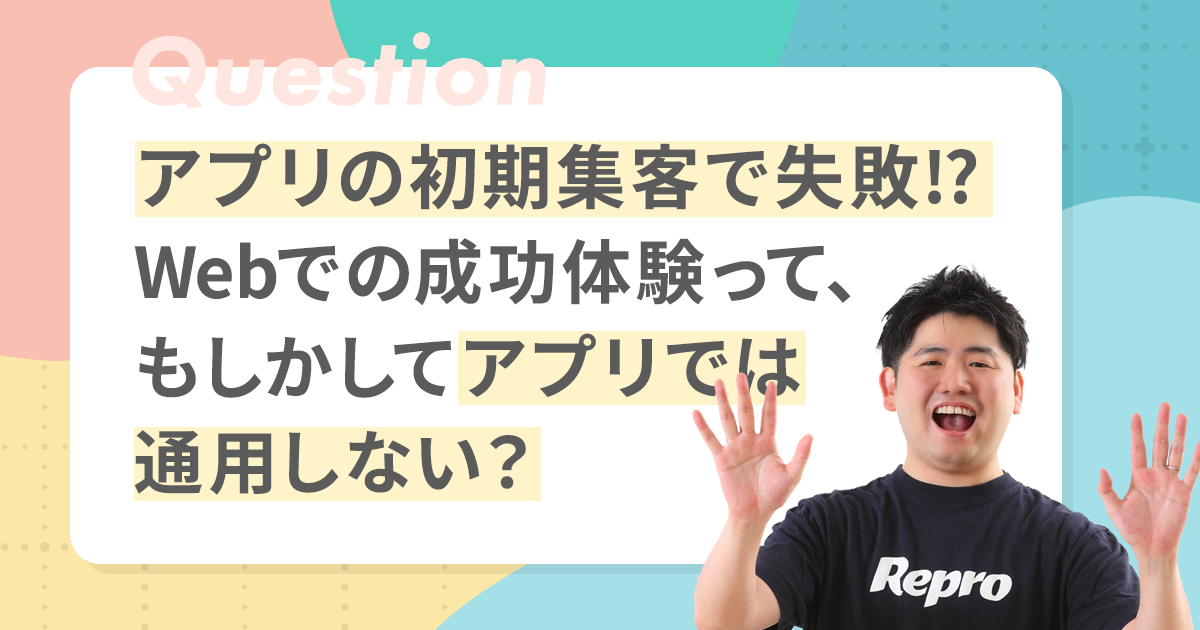

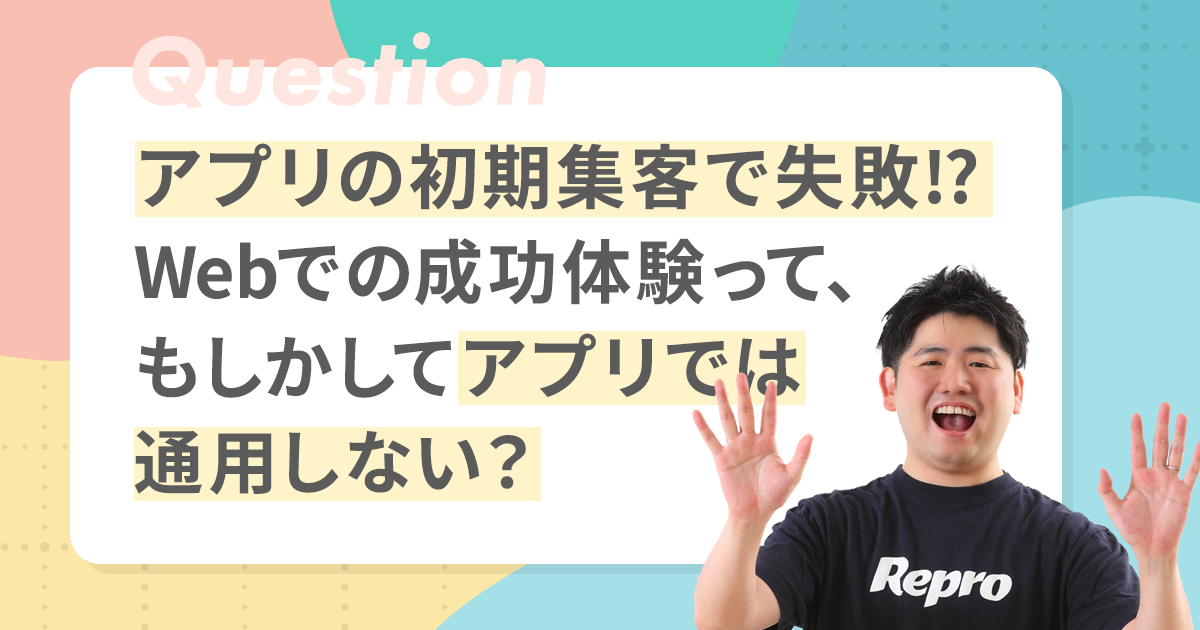
【今回のご相談】
今期、自社アプリを立ち上げたのですが、実は初期集客がうまくいっておらず、内心めちゃくちゃ焦っています。
我が社の事業としてはECサイトを運営していて、これまでサイト改善で実績を上げてきました。Webでは、SEOやLPOに強いメンバーが社内や協力会社にいて、私自身もわかる方なので、GA4を見ながら離脱やコンバージョンを追って臨機応変に対応してきました。ですが、どうやらアプリって同じようにやろうとしてもダメみたいですね。というか、できない。
広告は回しているのですが(予算はあります)、思うように集客できず……そこまではまだよいのです。今までもどうにかしてきました。しかしアプリでは何を改善すればよいのか。見当がつきません。代理店も何かが微妙です(何が微妙かはわかりません)。
先日、アプリ担当者が集まるオフラインのイベントに初めて参加してみました。こっそり他社の話に耳をそばだててみたのですが、計測するために必要なサービスを使っているとか、最近のトレンドとか、気になる話は聞けました。ただ、他の方も手探りでやっているような気がしたので深くは聞き出せず……。焦りばかりが募ります。(EC事業部、40代男性)
アプリを立ち上げても、「ダウンロード数が伸びない」「広告を出しているのに効果が見えない」といった壁に直面するケースは珍しくありません。
実はその原因の多くは、「Webマーケティングの常識をそのままアプリに当てはめてしまうこと」や、「リリース時点でデータ計測の基盤が整っていないこと」といった、本来なら避けられるはずの“落とし穴”にあります。
今回は、これまで200件以上のアプリ相談にお答えしてきたReproの中野が、アプリリリース直後の初期集客で失敗しやすい理由とその背景、そして成功につなげるために押さえるべきポイントを具体的に解説します。
「せっかくアプリをリリースしたのに、なかなか集客につながらない」。これは、多くの現場が直面している共通の悩みです。
そしてその原因は、「広告費が足りない」「プロダクトが弱い」といった表面的なものではなく、アプリマーケティングの前提や仕組みに対する理解のズレにあるケースがほとんどです。
まずはアプリの初期集客の失敗につながりやすいふたつの要因から順に見ていきましょう。
Web広告の運用に慣れている方ほど陥りやすいのが、「Webマーケティングと同じ発想でアプリ集客を進めてしまう」ことです。
「まずは流入導線のLPを作ろう」「コンバージョンはGA4で追えばいい」といった判断は、Webであればごく自然な選択肢かもしれません。しかし、アプリにおいてはこの前提そのものが異なります。アプリには独自のルールや制約が存在し、特に広告からの導線や計測環境の構築方法はWebとは大きく異なるのです。
また、アプリマーケティングは「初期の設計」で成果の大半が決まります。アプリに関する知見がないまま進めてしまうと「改善に必要なデータが取れない」「PDCAが回せない」といった事態に直結しかねません。
たとえば、どの機能がユーザーのLTV(顧客生涯価値)に貢献しているのか。どのチャネル経由のユーザーが継続的に使っているのか。アプリではこうした情報を細かく分析できますが、その環境を整えるには、事前の設計が不可欠です。
もうひとつ、アプリの初期集客が失敗しやすい根本要因として挙げられるのが、「データの取得環境を整えないまま走り出してしまう」ことです。
Webサイトであれば Google Analytics などで流入やコンバージョンを追えますが、アプリでは事情が異なります。ユーザーが広告をクリックしてストアに移動した瞬間にドメインが切り替わり、一般的な解析ツールではトラッキングが途切れてしまうのです。
そこで欠かせないのが、MMP(Mobile Measurement Partners/モバイル計測パートナー)と呼ばれるサービスです。導入することで、「どの広告チャネルからインストールされたのか」「そのユーザーがアプリ内でどんな行動を取ったのか」を可視化できます。
さらに近年では、AppleのSKAdNetworkに代表されるようにプライバシー規制強化の流れも無視できません。ユーザーの同意が得られなければ、広告接点のデータすら取得できないケースも増えています。
こうした背景から、広告媒体の管理画面の数値だけに頼るのは危険であり、信頼できる1stパーティデータを自社で取得・分析できる基盤づくりが、これまで以上に重要になっているといえます。
ここまで見てきたように、アプリ集客にはWebとは異なる前提と設計が求められます。では、実際の現場にはどのような“落とし穴”があるのでしょうか。
ここでは、アプリ初期集客で陥りがちな3つの失敗パターンと、その背景にある構造を解説します。

スタートアップや新規事業チームが陥りやすいのが、「事業計画に基づいたKPIが現実と乖離している」というケースです。
たとえば、「リリース初月に◯万人にインストールされ、◯%が課金する」といった数値が掲げられることもあります。しかし実際には、そこに明確なロジックがあるわけではなく、希望的観測になっているケースも少なくありません。
ほとんどのアプリには競合が存在し、ユーザーにとっての明確な“使う理由”がなければ選ばれません。加えて、リリース直後のアプリは導線や体験設計がまだ洗練されていないため、課金率や継続率は低く出やすい傾向にあります。
それにもかかわらず、過剰な期待値に基づくKPIを追いかけてしまうと、チーム全体が不必要に疲弊してしまいかねません。投資家や事業部の計画に基づく数字であっても、「現実的に到達可能かどうか」という視点を常に持ち続けることが大切です。
アプリ集客では「とりあえず思いついた媒体から始めてみる」という動きが多く見られます。代表的なのが「Apple Ads(旧Apple Search Ads)」や「Google広告」を戦略を立てる前の初期段階から利用するケースです。
もちろん、これらの媒体そのものが誤りというわけではありません。ただし、構造や配信ロジックを理解しないまま使ってしまうと、期待通りの効果が出ず、初期の貴重な予算を浪費するリスクがあります。
たとえば「AppleAds」の場合、検索ボリュームが少ないジャンルではインプレッション自体が出にくく、アプリの知名度がまだ低い段階では、そもそも表示すらされないこともあります。
だからこそ重要なのは、媒体ごとの特性やジャンルとの相性を理解することです。「どのチャネルなら、どれくらいのユーザー獲得が見込めるのか」を具体的な数値で見極めたうえで、戦略的に選定する姿勢が欠かせません。
アプリ立ち上げにおいて欠かせない要素のひとつが「どの支援パートナーと組むか」です。ところが実際には、「なんとなくアプリに詳しそう」「手数料が安いから」といった表面的な理由で選んだ結果、十分な知見や関心を持たないパートナーに依頼してしまうケースも少なくありません。
「支援担当者が実際にそのアプリを課金して使ったことがない」「アプリ特有の広告設計を知らず、Webと同じ運用をしようとする」といった事態が起きれば、チーム全体の方向性は簡単にズレてしまいます。
さらに、初期フェーズはPoC(実証実験)的に少額予算で進めるケースが多いため、“担当者ガチャ”が発生しやすいのも事実です。経験の浅いメンバーが担当につけば、本来得られるはずの示唆や改善サイクルが回らなくなるリスクが高まります。
もちろん、すべてを外部に任せる必要はありません。ですが「アプリを本気で伸ばすには、どんな知見・支援が必要か」という視点を持ち、必要に応じて信頼できる専門家を巻き込むことが、失敗を防ぐ有効な手段となります。
ここまで見てきたように、アプリの集客には「Webと同じ感覚で進めてしまう」「計測環境が整っていないまま走り出す」「非現実的なKPIを設定する」といった数多くの落とし穴が存在します。
では、こうした失敗を避けるために、最初に取り組むべきことは何でしょうか。
結論からいえば、「アプリに詳しい人に、まずは話を聞くこと」。これが、遠回りに見えても実は最も効率のよいやり方です。
実際の現場では、社内の新規事業チームが“自力でなんとかしよう”と手探りで進めることが多く、初期からプロの伴走を受けるケースは決して多くありません。ですがアプリマーケティングには、経験者でなければわからない前提や相場感、設計上の勘どころが数多く存在します。
たとえば、「このジャンルなら◯円程度で1インストールを獲得できる」「アプリストアでの表示を最大化するには、この導線設計が必須」といった知見は、支援経験のあるプロなら感覚として把握しています。
もちろん「やってみないとわからないこと」もあります。しかし、事前に押さえておくべきポイントを知っておくだけでも、失敗は確実に減らすことができます。特に、数値目標の妥当性、媒体のボリューム感、ターゲットユーザーの特性などは、プロの知見から“当たり”をつけてから動くことで、限られたリソースを無駄なく活用できるようになるはずです。
「アプリに詳しい人に相談したほうがいい」と言われても、初めての立ち上げでは「そもそも何を聞けばいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
最後に、初期相談で必ず押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

まず確認すべきは、「設定している獲得目標や予算が現実的かどうか」です。
現場では「初月で◯万DL、CPI◯円以下」といった数値が掲げられることもありますが、市場やチャネルの特性とズレているケースは少なくありません。
たとえ事業責任者や経営層が固定的なKPIを持っていたとしても、その達成可能性や実現の道筋については専門家の意見を聞くことが重要です。「そのままでは難しい」「こうすれば近づける」といった率直なアドバイスを得ることで、現実的な戦略を描きやすくなります。
次に大切なのが、「リリース後の成長プロセスをどう描くか」です。
立ち上げ直後はどうしても目の前の施策に追われがちです。しかし、全体の流れを把握していなければ、優先順位を誤り、リソースを無駄にしてしまうリスクがあります。
グロース経験のある専門家に相談すれば、「似たジャンルのアプリで直面した壁」「どのタイミングで改善が効いたか」といった暗黙知に触れることができます。こうした知見は、自分たちの現在地を客観的に把握し、次の一手を正しく選ぶための指針となります。
最後に確認したいのは、「改善サイクルを回せる環境が整っているか」です。
アプリはリリースがゴールではなく、むしろそこからが本番。成功を左右するのは“リリース時の完成度”ではなく、“リリース後にどれだけPDCAを回せるか”です。
そのためには、「どの機能で離脱が起きているのか」「課金につながった導線はどれか」「どのチャネルがLTVに寄与しているのか」といったデータを取得できるよう、事前に設計しておく必要があります。
とはいえ、「どんなデータを、どの粒度で追うべきか」は、経験がないと想像しづらいもの。だからこそリリース前に専門家へ相談し、
を確認しておくことが大切です。これによって、PDCAの“回転数”と“深さ”を同時に高めることができます。
ここまでご紹介してきたように、アプリの立ち上げには多くの落とし穴があります。
こうした課題に直面していても、日々の業務に追われながらひとりで判断し続けている方は少なくありません。
Reproでは、アプリマーケティングの最前線を知る専門家が直接お話を伺う「無料相談会」を開催しています。
「今の施策は正しい方向に進んでいるのか?」
「限られた予算をどこに投下すべきか?」
「リリース後に改善を回せる仕組みをどう整えるべきか?」
そんな悩みをお持ちの方にとって、具体的な指針を持ち帰っていただける場です。ぜひお気軽にご活用ください。
▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。