2025.08.14
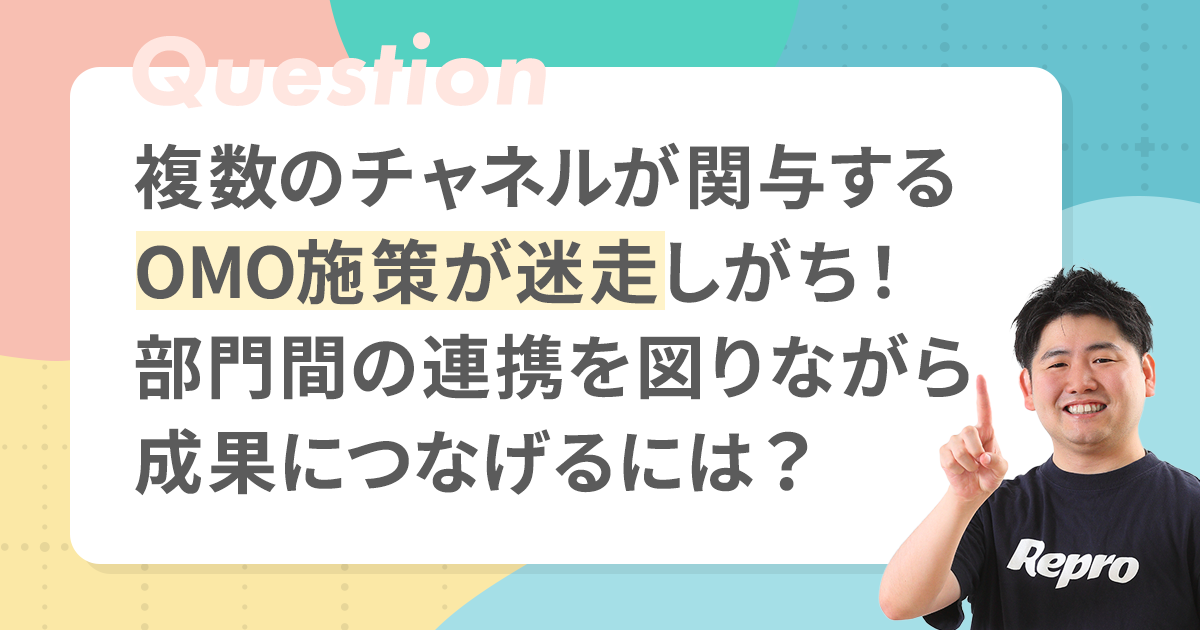

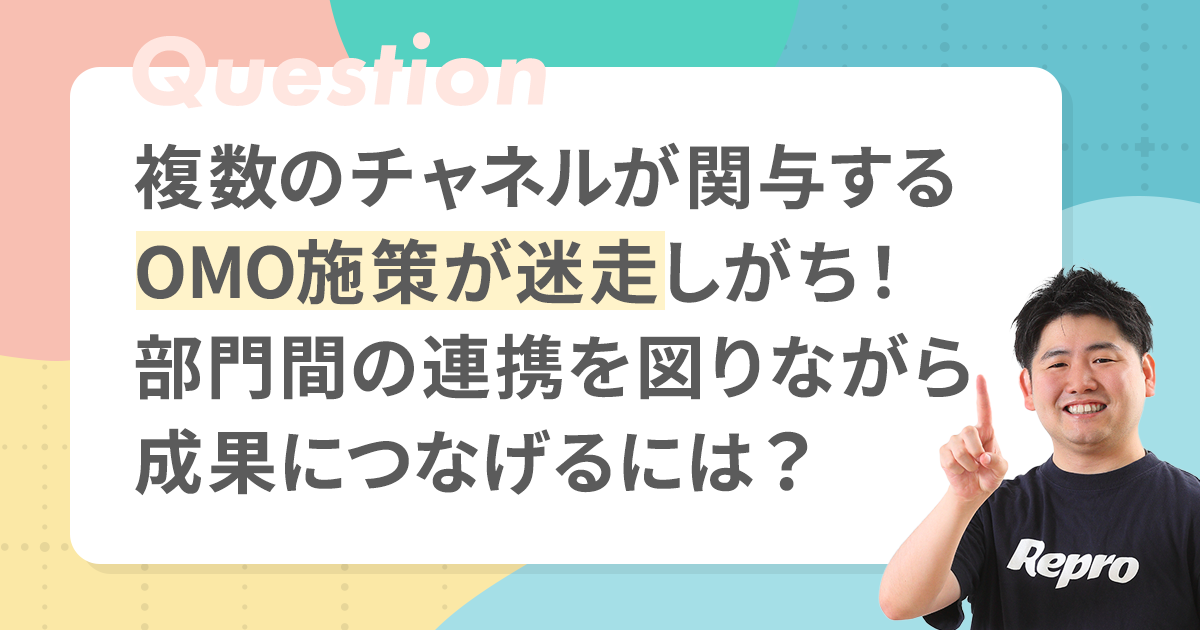
【今回のご相談】
前回(OMO施策の成果を分ける“店舗での体験設計”とは?)に引き続きのご相談です。おかげさまで店舗とデジタル側との分断を乗り越える方法は見えてきました。一方で、「店舗からのDL数を伸ばしたい」という私たちデジタル部門の思惑に対して、店舗からは「アプリやECに売り上げを持っていかれたらどうすればいいんだ」「プッシュ通知などで店舗への来店を促進させてほしい」といった疑問や要望も出てきています。議論が活発になるのは良い傾向だと思うのですが、今のように各々が目先の指標を改善させようとするだけでは、うまく全体がかみ合っていない気がするのです。
余談ですが、これを機に私が担当しているデジタル部署の主導で、よく言えば各部門間の連携を深めていきたいと目論んでいます。語弊を恐れずに言えば、この流れに乗って店舗側の動きまでデジタル側でできる限りコントロールしていきたい……そんな思惑もあります。とはいえ、これまた何から始めればよいのやら。(アプリ・Webマーケ兼務、40代男性)
アプリ・EC・店舗・CRMなど、複数のチャネルが関与するOMO施策では、オペレーションや顧客体験が複雑になることで、「何を、なぜ改善すべきか」が見えづらくなる場面も少なくありません。
その結果、今回の例のように、OMO施策を行っていても効果がうまく可視化できなかったり、複数の部署が関わることで共通の認識ができておらず今後の方向性が定まらないまま迷走してしまう……そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした状況のなかで、部門間の連携を図りながら成果へとつなげていくためには、KGI(最終成果指標)から逆算し、施策レベルまで指標を構造的に設計する「KPIツリー」の構築と活用が不可欠です。
今回は、OMO施策に特化したKPIツリーの考え方から、設計のステップやつまずきやすいポイント、代表的な構造パターンまでをご紹介します。
OMO施策では、アプリ・EC・店舗といった複数のチャネルが関与することで、顧客体験が多層化し、施策同士の因果関係が見えにくくなりがちです。「アプリのDL数は伸びているのに売り上げにつながらない」「部門ごとのKPIがバラバラで、全体像が見えない」といった声が現場で聞かれるのも、その一例です。
こうした課題を乗り越えるうえで、指標同士のつながりを整理し、改善すべきポイントを見極める“ものさし”として活用できるのがKPIツリーです。KPIツリーを使えば、指標同士のつながりを可視化できるため、「どこをどう改善すべきか」が明確になります。その結果、施策全体に一貫性が生まれ、現場の動きも加速しやすくなります。
【関連リンク】KGI・KPIとは?誰でもわかる意味の違いと設定例・KPIツリー構築
KPIツリーとは、最終目標であるKGIを起点に、売り上げや来店といった成果に至るまでのプロセスを段階的に分解し、施策レベルのKPIまで落とし込んだ構造図のことを指します。
OMO施策において、KGIとしてよく設定されるのは以下のような指標です。
KPIツリーでは、こうしたKGIを「売上=購入数 × 客単価」といった基本構造に分解し、さらにその下層に「DL数」「訪問率」「購入率」「アプリ提示率」といったKPIを配置することで、施策全体の因果構造を視覚的に捉えられるようになります。
KPIツリーを設計する際に陥りやすいのが、「今ある指標をどう改善するか」という考えを起点とする、“指標先行型”の思考です。今回のお悩みでも、各関係者は目先の指標にとらわれているようでしたね。このアプローチには、以下のような落とし穴があります。
「DL数を伸ばしたい」「プッシュ通知の開封率を上げたい」といった施策単位のKPIを起点に設計を進めると、それらの指標がKGIにどう結びつくのかが曖昧になりがちです。
その結果、数値の改善は見られるものの、それが成果に直結せず、組織としての手応えを得られないという事態に陥るおそれがあります。

部門ごとに独立したKPIを設計してしまうと、アプリ・EC・店舗といったチャネルごとに方向性の異なる施策が展開され、結果として組織の足並みがそろわなくなります。
このような状態では、部門間で「何を優先して改善すべきか」が共有されず、連携そのものが困難になるという課題が浮上します。

KGIから逆算してKPIを設計することにより、OMO施策全体に構造と整合性を持たせることができます。ここでは、KGI起点のKPIツリー設計によって得られるメリットをふたつご紹介します。
OMO施策では、チャネルごとのデータや顧客体験が複雑に絡み合うため、「どこに課題があるのか」が見えにくい場面も少なくありません。
KPIツリーを構築し、実際の数値をあてはめることで、どの段階にボトルネックがあるのか、どの指標が優先的に改善すべきかを構造的に把握することができます。

OMO施策では、アプリ部門と店舗部門の間に意識のズレが生じることもあります。店舗では「アプリ施策が進むと、店舗の売上が減るのではないか」といった懸念が持たれることも珍しくありません。
こうした場合、KPIツリーを活用することで「アプリ施策が店舗売上にどう貢献するか」を可視化できるようになり、部門間の協力体制を築きやすくなります。
KPIツリーを単なる図にとどめず、実際の改善サイクルに活かしていくには、設計から運用までを見据えた視点が欠かせません。ここでは、そのための3つの実践ステップをご紹介します。
KPIを定義しても、その数値を継続的に取得・管理できなければ、PDCAは回せません。特にパッケージ型アプリを利用している場合、「この数値はそもそも取得できない」といった仕様制限がある場合もあります。
そのため、KPIを定義する前に、取得可能な指標やデータ形式を確認しておくことが前提となります。場合によっては、取得のための設定変更やツールの追加も検討が必要です。
KPIは施策の成果を見るだけでなく、顧客が体験するプロセスを可視化する手段でもあります。
たとえば、以下のような一連の体験を想定した場合、
この体験をKPIとして落とし込むと、
といった指標が見えてきます。顧客体験から逆算してKPIを設計することで、より意味のある数値管理が可能になります。
アプリ、店舗、CRMといった複数部門が関与するOMO施策では、それぞれが独自のKPIを追うことで、施策全体の整合性が崩れ、因果関係も見えにくくなってしまいます。
このステップでは、各部門が持つKPIを一度棚卸しし、それらを顧客体験の流れに沿って再配置・接続していきます。たとえば、
こうしたバラバラの指標を、「アプリを軸にした購買行動の流れ」として1本の線でつなぐことで、部門をまたいだ施策の一貫性と、組織全体の連携を生み出すことができます。
次に、OMO施策における代表的なKGIを起点とした、ふたつのKPIツリーパターンをご紹介します。

たとえば「EC売上」をKGIに設定した場合、「売上=購入数×客単価」→「購入数=訪問数×購入率」……というように、因果関係を分解していきます。
購入数や単価といった構成要素を起点に、さらに「新規客数」「購入率」などを紐づけていくことで、売り上げを生む構造全体を見渡せるようになります。

「アプリ経由の店舗売上」にフォーカスしたツリーを設計する場合、「ダウンロード済み店舗購入客数」「アプリ提示率」など、アプリとオフラインが交差するポイントをしっかり押さえることで、その後の改善フェーズにおいても部門間の連携を取りやすくなります。
ふたつの例のように、「売上=購入数 × 単価」の考え方を起点とし、さらにその下層に「購入数=新規購入客数+既存購入客数」といった成果の実現に必要な要素を広げていくKPIツリーの考え方を取り入れれば「どこにボトルネックがあるのか」が自然と見えてきます。
OMO施策の複雑性を乗り越えて成果を出すためには、KGIから逆算したKPIツリーを軸に、全体構造を見渡す視点が不可欠です。
一般的に、こういったKPIツリーを作って施策を統括するのは事業部長クラスになるかと思いますが、今回のケースのOMO施策のように関係する部署が分かれている場合、デジタル部門主導で動くことが多いようです。
KPIツリーを通じて、「どの施策が何につながるのか」を部門横断で共有できるようになれば、単なる数値改善ではなく、事業成果につながる本質的なPDCAを組織全体で回していくことができます。
Reproでは、OMO施策におけるKPI設計から、データ取得基盤の整備、施策運用の改善までを一貫してご支援しています。「自社の指標を棚卸ししたい」「まずは壁打ちから相談したい」といった段階でも、お気軽にお問い合わせください。
もし自社での施策立案や検証に不安がある場合は、Reproのアプリ収益最大化サービスをご活用いただくのもひとつの選択肢です。無料相談も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
様々なアプリ・WebビジネスのKGIを適切なKPIへとブレイクダウンし、KPIツリーを作成した事例集を公開しています。KPIの設定に悩んでいる方はぜひご覧ください。ビジネスモデルごとに特徴的な課題の改善方法を紹介しているので、成果改善に直結するはずです。
▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。