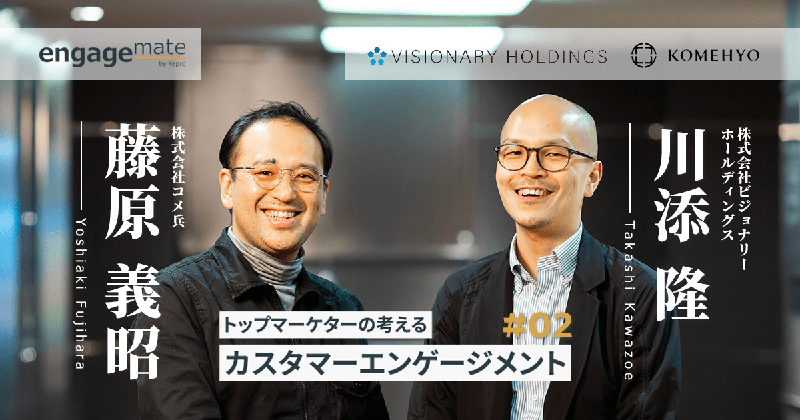テクノロジーの飛躍的な進化によって、顧客と企業とのタッチポイントがあらゆる場面で存在するようになった現在。「モノを購入する体験」も、大きく変化してきています。消費人口が減り、流行の変化も高速化する中で企業が選ばれ続けるには「顧客エンゲージメントの向上」が不可欠な時代になりました。しかし、本当に顧客に向き合ったコミュニケーションを実現するには組織全体が顧客目線を持たなければなりません。
では、ユーザー環境が激しく変化する中で、カスタマーエンゲージメントを実現できる組織はどう作ればよいのでしょうか。顧客目線での体験向上を生み出してきた、株式会社コメ兵の藤原義昭氏と株式会社ビジョナリーホールディングスの川添隆氏を招き、対談を行いました。
「もう一度行ってもいいかな」と思ってもらうために
――これからの時代、カスタマーエンゲージメントを意識した事業運営の必要性があるのではと考え、お二人の対談を実施させていただきました。まず、そもそもお二人が考える、カスタマーエンゲージメントがどんなものか、お聞かせいただけますか?
藤原氏(以下、藤原) 時代の変化に伴って、消費者が何かを欲しいと思ったときの情報の取り方も大きく変わっています。昔は「ロレックスが買いたい」と思ったら、店員さんに聞けば詳しく情報を教えてもらえた。ところが、今は自分のスマホで調べられるし、なんなら店員さんよりも詳しくなることだってできるわけです。

川添氏(以下、川添) 藤原さんがいるコメ兵が運営しているWebメディア『トケイ通信』でも、お客様が商品についての適切な事前知識を得られること目的にしているのではないですか?
藤原 そうですね。商品選びに役立つ情報は、店舗に来ずとも入手できるようネットでも発信していきたいと思っています。一方で、店舗販売は別の角度から提案ができることが強みです。製品自体の性能はどの店でも変わりませんが、ライフスタイルからの提案は人がいるからこそできることなので。
極端な例ですが、ロレックスを欲しがっている方が目の前にいたとして「来週、アウトドアに行くんですよ」と話をしてくれたら、「それなら、今回はG-SHOCKの方が……」と提案ができるかもしれないですよね。
川添 メガネスーパーをはじめとする当社グループの場合、販売店舗はその“オーダーメイド”をまさに強みにしています。メガネってお客様が事前に調べあげてから来店してくださるケースは少ないのです。だから、お客様にとって「これが欲しい」だけでなく、「本来解決したい課題」、つまりユーザーニーズをその場で的確に把握しないと、間違ったレンズを提案しかねない。専門知識と接客、それぞれの面からナーチャリングできないと満足いただけません。
起こりやすいのが、遠近両用レンズを求めて来店されるお客様とのすれ違いですね。遠近両用レンズって“限定的な狭い視野で近くが見える、遠くを見るためのメガネ”なんです。けれど、名前の印象からその事実が伝わっていないので、メガネを作ったあとにニーズを満たしていない、となるケースも珍しくありません。

藤原 そうなんですか。コメ兵の場合、商品の買取は顧客ニーズの把握が難しい仕事なんです。顧客目線で考えたら、ベストは「高く売れること」でしょう。ただ、じゃあ1,000円高く買ってくれる店舗を探してあちこち回るかどうかというと……。そんなことはないかもしれないですよね。
買取価格はあくまで相場。企業ごとに誤差があるのは必然なんです。なので、他店舗と比較して「気持ちよく売れた」と感じていただけるような仕組み作りをしなければと考えています。
そのため、なぜその値段になるのかを詳しく説明したり、テクノロジーを導入して店舗の混雑を少しでも緩和しようとしたりしているんですね。「もう一回、行ってもいいかな」と感じていただけるようにしたいな、と。
川添 以前、そのためにAIを導入する必要性があるのかもしれないってお話をしてらっしゃいましたよね。人員削減ではなく、カスタマーエンゲージメントの向上を目的としたテクノロジーの導入はプラスなのでは、と。
藤原 はい。例えば、買取をする上で重要な「真贋作業」は、人力だと1商品あたり数分はかかってしまうんです。でも、それをAIの力で0秒にできれば、待ち時間は大幅に減らせますし、その時間をお客様とのコミュニケーションに当てられます。今後導入を予定している「AI真贋」の場合、ルイ・ヴィトンを見分ける鑑定精度は97%以上です。
さらに、テクノロジーを使えば、業務は属人化しにくくなります。その結果、統一された接客がより容易に実現でき、顧客体験をさらに豊かにすることにエネルギーを使えるのではないかと考えています。
戦略立案者と実行者の見ている景色は違う? 顧客体験改善のために「組織」ができること
――顧客体験の改善となると、組織全体での意識改革が必要なのかなと思います。部署や部門ごとに何を意識するべきなのでしょうか?
藤原 大前提として、社員全員が同じだけ意識を高めないと組織は変わりません。店舗のメンバーはお客様と実際に触れている身で、その現場の声を拾って解釈するのがマーケティングメンバーの役割です。異なるケイパビリティの各部署が連携し合いながら、顧客体験の向上を目指す必要があります。

川添 コメ兵は縦割りの組織なんですか?
藤原 2011年ごろまでは商品ごとの事業部でしたが、現在はバリューチェーンで機能組織を編成しており、仕入れ・販売・物流・マーケティングなど分かれていますね。事業部制のときは、プロダクトごとに売上競争が生まれるのでトップラインを目指すためには良かったのですが、フロアごとに接客の仕方が違ってきてしまい……。そうなると、事業部制では顧客体験向上は望めないと感じました。
川添 うちの場合は、事業部制と機能制の部門を両方持っています。メガネやコンタクトレンズ、補聴器などはプロダクト単位で事業部を作った方がわかりやすく、マーケティング、デジタル・EC、物流などは横串で機能しています。
昔は店舗ごとの単位でも縦割り組織だったようで、創業オーナーからの売上目標も厳しく……(笑)。今はプロダクトごとに目標を置きつつも、マーケティング、デジタル・EC、物流などの機能的な部署が一貫して各プロダクトを見ているのでカスタマーエンゲージメントは最大化できているように思います。
8年間、赤字の状態が続いて足元の事業をなんとかするしかないフェーズがあったのですが、今は状況が改善し、マーケティング部門のメンバーがLTVやリピート率の向上を考えられるようになったので、先をいく施策を考える体制が整ったように思っています。
足元の事業を見つめるしかないときには、なかなか未来のことは考えにくいですよね。

川添 店舗のメンバーも、本社でマーケティングや商品のような戦略に関わるメンバーも、赤字だとさすがに希望が持ちにくいですからね……。特に店舗で売上を立ててくれているメンバーは、なかなか商品が売れない状況に頭を抱えていた時期もありました。
その後、試行錯誤する中で独自性とその結果がついてきたタイミングが2014年。そこから“「アイケア」というソリューションの提供によって人々の人生を豊かにする”ことが、メガネスーパーの大義だと社内外に宣言をしたんです。そうしたら、社内全体が目標を持って走れるようになってきたと感じています。
――具体的にはどんな変化が?
川添 「アイケアカンパニー宣言」をきっかけに、店舗のメンバーはその日その日の利益を考えながらもお客様への最適な提案していくようになり、本部のメンバーも短期的な利益の最大化だけでなく、少し先の未来を構想するようになっていったように思います。ある程度の役割分担とそれぞれの協力体制ができたことで、長期的なカスタマーエンゲージメントの向上を考えられるようになりました。
藤原 会社って戦略を立てる人と実行する人が違いますからね。だからこそ、メンバー内での意思統一が本当に重要だなと思います。戦略立案者に明日の売上は作れないけれど、3年後の未来を描くことはできますから。
全員が同じことをする組織は良くないですよね。事業には時間軸がありますし、短期も長期も考えなければならない。一番長期スパンで考えるのが経営者の仕事。そんなふうに解釈しています。
川添 藤原さんは、現在は事業のどのあたりを考えることが多いのですか?

藤原 僕は未来を考えるポジションですが、その中でも特に「緊急ではないけれど重要度の高い」ことを考えるよう意識しています。現場での細かな状況は僕にはわかりませんが、3カ月後の施策は頭の中にありますし、もちろん戦術ベースに留まらない戦略ベースの話も考えています。3年がかりの大きなものだったりしますけれどね。
トップがビジョンを見せることで文化が生まれる
――そういった役割分担がしっかりとなされているのは、理想的な組織のように思えますね。社内でその雰囲気を作るにはどうしたら良いのでしょうか?
藤原 商品をお客様の元に届ける行為のみであれば、自動販売機であろうが店舗であろうが、どちらでも良いはずです。でも、あえて店舗で接客したいと思うのは、目の前のお客様に最高の体験を届けたいからですよね。そして、その想いは会社の文化が作るものです。
社員一人ひとりの意識変革を促すのは、その会社組織が作り出した文化だと思っています。文化は会社のビジョンによって生まれます。トップがビジョンを見せる、語る、作ることで、仮に明文化されていなくても組織の中には文化が生まれます。
例えば、コメ兵には“迷ったら「まじめ」を選ぶ”というクレド(行動指針)があり、倫理観を高く保つ文化なんです。これは、あくまでお客様の信用を大切にしようと誰もが思っているから生まれました。リスクを取るのではなく、お客様の信用・信頼を意識すると「やらない」決断も往々にしてあるはずですから。社員一人ひとりが、倫理観を指針に行動しているように思いますね。
川添 文化の基礎を作るのが経営トップのビジョンや倫理観で、そこに基づいて行動するのが社員ですよね。だから、ビジョンのない会社は働きにくいと思います。自由とか裁量が大きいとかってよく言われる組織の理想像ですが、指針がないと正誤の判断も付きませんからね。

川添 また、そういった文化はトップダウンでは根づきにくいものでもあります。社員としてできることは、一人ひとりがお互いを巻き込みながら会社の文化を実行に移す、というか。だから、経営者はHOWを伝えるのではなく、WHYを伝えるのが大切です。「どうしてやるのか」を伝え、まずは旗を振る。すると、RPGのように仲間が集まり、ロイヤリティが生まれ、一方向に向かって走れる組織になるように思います。
もちろんその過程では、メンバーが視座を上げないといけない瞬間もありますし、経営者に対して「こうしましょう」と提案しないといけない瞬間も訪れるので、難しいときもありますけれどね。
投資しないとすり減っていく、ブランドという「資産」
藤原 経営者が創業者ではない会社だと、そのバイタリティを維持するのが難しそうですよね。過去の成功体験に縛られて新しいことを何もしていないので、積み重ねてきたアセットをすり減らしているだけ、というか。
ブランドをBS(貸借対照表)とPL(損益計算書)に例えて考えてみると、わかりやすいです。BSの「資産」をブランドと考えたとき、PLの純利益やBSの純資産を投資に当ててブランド価値を高めていく必要があります。
 藤原氏が書いた「ブランドのPLとBS」の図
藤原氏が書いた「ブランドのPLとBS」の図
藤原 ところが、過去の成功体験を引きずっている会社は、投資を行わないためにブランドという資産の価値をすり減らしているわけです。
その上、ビジネスでいう「ヒト・モノ・カネ」といった資産は、マーケティング的に考えると「人材・ブランド・情報」と置き換えられます。このうち、ブランドや情報はPLにもBSにも掲載されない項目。財務諸表には見えないからおざなりにしがちですが、放っておくといつかすり減り、ブランド価値は消えてなくなってしまいます。
いかに既存のブランドを活かしながら、投資を続け、核となる事業を大きくするのか。これを意識するのが、これからの時代のビジネスを形作る上では重要な気がします。

――ブランド価値を正しく測る指標って存在するのでしょうか?
藤原 なかなか難しいです。現状だと、数値ベースで測れるのはNPSくらいではないでしょうか。ブランド価値って、スポットではなく時間軸での変化が重要ですし、他社との相対評価ではなく絶対評価で考える必要がありますからね。
そして、その評価をエンゲージメントとつなげて判断するのもまた難しいです。とはいえ、LTVであれば数年単位の期間にかけて測定を続ければある程度は見えてくることもあるのかなと。
評価は金銭よりも感情を優先して
――カスタマーエンゲージメントを大切にする組織へ変えていくには、人事評価の基準も重要だと思います。従業員に対してはどのような評価制度を設けているのですか?
藤原 社内の評価制度では、感情報酬を意識していますね。仮に月収が1万円上がったとしても、僕らはその給料にいつか慣れてしまうんです。つまり、金銭的評価は、ある程度のところで麻痺を起こす。その上、何千人もいる社員の報酬を少し上げただけで、経営を大きく圧迫してしまう。MVP制度も重要ですが、そこでも報奨金を設けないことが大切だと思っているんです。
金銭的な報酬には限界がある。特に、今の時代は感情報酬を届ける文化や仕組みを作るのが何より重要だと思いますね。

――どうやって感情報酬を届けているんですか?
藤原 コメ兵には上司や仲間からの「ありがとう」を伝える習慣があり、“ファイブスター”というクレドの体現者に贈る賞もあるんです。胸元に付けられる小さなバッジを贈呈するもので、金銭的な報酬と比較すると、相対評価しにくい価値なので個人の中にも強く印象に残ります。
川添 賞金はなく、バッジをもらえるだけ、ということでしょうか?
藤原 そうです、そうです。お客様には何のバッジかもわからないですし、バッジがもらえるだけ。でも、やっぱり嬉しいものだと思うんです。
川添 「こんな活動をしている〇〇さんはすごい」をしっかり伝えることが大切ですよね。感謝の言葉もそうですが、複数の役割を持っている、みたいなチャンスを取りにいく姿勢を評価できたら良いなと思います。当社グループでは1人が複数の役割を担う「クロスファンクション」を推奨していますが、各所で行動している人って能力も上がるし、活躍の場もそれだけ多いですからね。
当社の代表は「金銭的な分け前は、いつだって上げたい」と常々言っています。でも、KPIの達成が報酬に直結するわけではないから、誰しもが納得できる、報酬を上げるべき言い訳(理由)を作っておくことが重要だなと思います。

川添 逆説的ですが、個人として先に金銭的な報酬を取りにいこうとすると、その分責任が大きくなるので、ミスマッチが起こりやすいと思います。そうではなく、責任を取りに行って成果を出す。逆に会社としては、責任を先に渡してから報酬を上げる。この方が適度なプレッシャーを保った状態で仕事に取り組めるはずなんですよね。市場価格目一杯の報酬をもらってしまうと、会社から切られるリスクが伴うので、本来の実力を発揮できなくなりやすいというか。
「言い続ける人」が輪をつくり、組織全体を変える
――最後に、今後、カスタマーエンゲージメントの向上を意識した組織を作りたいと考える企業の方に向けて、お二人からメッセージをいただけますか?

藤原 本来であれば、まずはトップがしっかりと旗を振ることが大切です。ただ、そういう立場ではない場合は、とにかく時間をかけて変化を促すしかありません。数カ月ではなく、少なくとも1年間ほどの時間をかけて同じことを言い続けて行動を続けることを意識してみてはどうでしょう。
カスタマーエンゲージメントの向上も、日々の仕事を良くするためにも、ステークホルダーを巻き込みながら組織を変えていく必要があります。その変化は「言い続けている人」が輪を作って起きるんです。つまり、日々語り続ける人がいることで「あの人が言っているなら」と周囲も協力的になる。そして、それに影響されて、組織全体も変わっていくはずですから。
世の中のビジネスパーソンの中には、我慢できずに「もうだめだ」とくじけてしまったり行動をやめてしまったりすることが多い気がしています。ですから、とにかく言い続けて行動する。それを徹底してみては、と思いますね。
川添 言い続けて信頼を得るためには結果が必要ですよね。僕も、前職時代に社内での権限が十分になく施策や体制の変革などができない時期がありました。でも「常にお客様のことを考え、ブランドとしてあるべき価値を提供したい」と言い続けていたら、周りから責任者へ推薦してもらい、パフォーマンスを発揮できた経験があるんです。
そうやって言い続けるには、本質的な意味で会社の文化や、ブランドとお客様の関係性を信じる必要があります。どこかで諦めたり投げ出したりしてしまうのは、事業を他人事だと捉えているからではないでしょうか。達成したい理由を自分の中に強く持ち続けられることも重要だと思います。
僕はそれを“コミットメント”と呼ぶのですが、おそらくベンチャーが組織全体で前へ前へと進められるのはそのコミットメントが強いからだと思うんです。ムードがあるから動きやすい、というか。
僕自身もこれまでくじけそうになったこともありましたが、待ってくれているお客様もいるし、変えずにはいられないと強く思って行動してきました。胆力を求められますが、乗り越えるとビジネスパーソンとして一段階上に登れるように思いますよ。
(執筆:鈴木しの 撮影:栃久保誠 編集:鬼頭佳代/ノオト)
※本記事に掲載されている取材内容、プロフィール等の情報は、2020年3月11日時点のものです。