2019.06.06
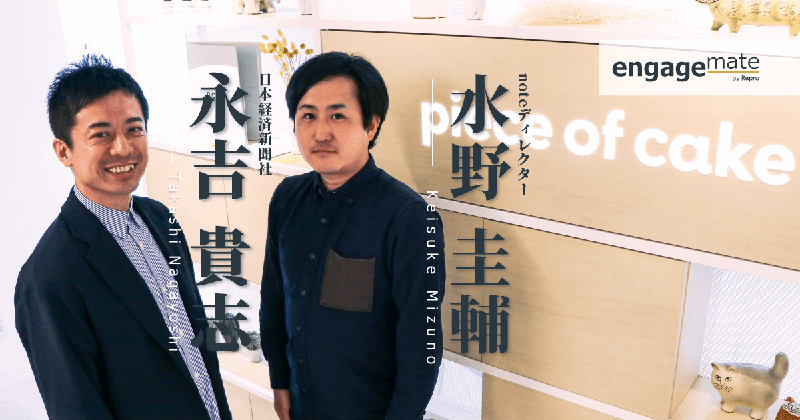
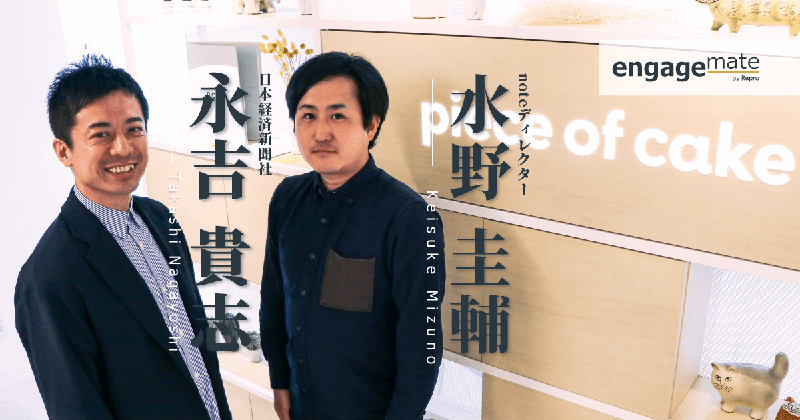
サービス成長に携わるすべての人を応援するためのEngagemateのインタビュー企画。今回は「メディア企業によるリアルコミュニティ作り」というホットなテーマに取り組む、2人の仕掛け人のお話をお届けします。
2019年2月に日本経済新聞とnoteが共同プロデュースで開始したコミュニティ「Nサロン」は、100名の定員に対して2倍以上の申し込みがあるなど大きな注目を集めています。
今回はNサロンのブランドづくりを担当し、わずか3ヶ月で自走するコミュニティへと育て上げた日本経済新聞社の永吉氏とピースオブケイクの水野氏に、Nサロン誕生の背景と展望についてたっぷり語っていただきました。

――はじめに、Nサロンの活動について教えてください。

水野 Nサロンは、「ビジネス」の日本経済新聞社(以下、日経)さんと「クリエイティブ」に強いピースオブケイクの良いところをかけ合わせて、あらゆる人にとっての「学びの場」を提供するコミュニティです。
具体的な活動としては、デジタルネイティブの若手と各業界のエグゼクティブによる「トークセッション」や、サロンメンバーならいくつでも受けられる「ゼミ」の開催など、参加者にとって新しい学びと経験が得られるようなコンテンツを提供しています。
2019年2月から期間限定でコミュニティがスタートし、5月にいったん終了したところです。
――もともとどういった経緯で「Nサロン」は立ち上がったのですか?

永吉 「Nサロン」を立ち上げるきっかけとなったのは、私たち日経が手がけた「COMEMO(コメモ)」というサービスでした。
COMEMOは意見を発信したいビジネス・経済の専門家と新たな視点や気づきを得たいビジネスパーソンが出会うコミュニティで、オンラインだけでなく多くのリアルイベントを開催していました。
水野さんと一緒に働くようになったのもCOMEMOがきっかけでしたね。
水野 そうですね。ピースオブケイクと日経が資本業務提携をしたこともあり、いつの間にか毎週がっつり顔を合わせるようになってました(笑)。
単発のイベントをやっていく中で、「より未来につながるような連続的な場を作りたい」という気持ちが生まれていきました。
単発イベントは集客に毎回苦労しますし、終わりが見えないという問題もあります。ですから、ある程度クローズドな場の方が継続性と広がりが生まれるかな、と。
元々、僕自身がいくつかのオンラインコミュニティに所属していたこともあり、固定のメンバーで継続的に学びを得られる仕組みに面白みを感じていました。そこで、永吉さんを始め日経のみなさんにオンラインコミュニティの話をしたところ、かなり興味を持っていただきました。
それを機に徐々に企画を詰めて、満を持して始まったのがNサロンというわけです。
――Nサロンのコンセプトは、どのようにして固めていきましたか?
水野 Nサロンを立ち上げるとき、『TED(テッド)』のように、いろいろな人がアイデアを伝えられるような場にできたらいいなという想いを軸にコンセプトを決めていきました。(TED:Technology Entertainment Designの略で、世界中の著名人によるさまざまな講演会を開催・配信している非営利団体のこと)。
Nサロンの「ビジネスとクリエイティブが化学反応を起こす場を。」というコンセプトは、まさにビジネスの代名詞ともいえる日経さんと、さまざまなコンテンツが混在して「クリエイティブ」を大切にしている弊社のイメージから生まれました。
まだまだ完全ではありませんが、コンセプトに込められた多様性が、登壇者を決めたり、イベントの内容を考えたりするときの軸になっています。
永吉 通常、こうしたコミュニティづくりは短期的なメリットを追いかけると、「日経電子版ユーザーの獲得にどうつなげるか、いつになったらいくら儲かるか」というよくある話になってしまいます。
ですから、社内向けには、あくまでも中長期の種まき的な視点で説明することを意識しました。
コミュニティは今後なにかしらのビジネスの土台になっていくので、今は見えなくても必ず出口は見つけられると話を通し、短期的なメリットを追求するのはきっぱりとやめました。

――コミュニティの可能性を伝えることで社内の合意を得られたんですね。
永吉 そうですね。日経も転換期にあります。これまで144年間記事を作ってきましたが、今後は記者だけが記事を生み出すのではなく、周辺の人と一緒になってコンテンツを作っていくことが大事なんじゃないかと。
日経の得意領域であるビジネス分野だけでなく、Nサロンでnoteさんとコラボすることで、それ以外の領域も取り込むことができるし、その結果ビジネスパーソンの生活が前進すればそれでいいんじゃないか、という結論に達しました。
水野 うちとしては自由に泳がせてもらったという感覚があるんですよね。日経さんは歴史ある大手企業ですが、うちはスタートアップなので、社内の稟議をとるというよりも、加藤(ピースオブケイク代表 加藤 貞顕氏)と立ち話でOKが出ればいいみたいな部分もあります。
しかし、その分、提供するコンテンツの質には徹底的にこだわっています。「クリエイターファースト」かどうかは常につきつけられました。例えば、トークセッションの登壇者選びにおいても社長から「その組み合わせで面白い化学反応が起きるのか?」「登壇してくれるクリエイターには、どんなメリットがあるのか?」といった厳しいツッコミは節目節目で入っています。

クリエイターへのリスペクトが詰まったフィードバックや2社ならではのコラボを生み出すために苦労しました。
良いテーマが決まっても登壇者の組み合わせで頭を悩ませたり、人選が決まっても日程調整が難しかったり。しかし、大変な想いをして生み出したトークセッションほど盛り上がり、クローズドにするのがもったいないくらいの仕上がりになりました。たとえば、ホテル経営者同士の組み合わせで、東大生で経営者の龍崎翔子さん(L&G GLOBAL BUSINESS 代表)と星野リゾート代表の星野さんの組み合わせは日経さんとnoteならではの絶妙なマッチングだったと思います。
――Nサロンを設立する際に、とくに苦労されたポイントを教えてください。
水野 要所要所で手伝ってくれたスタッフはもちろんいるのですが、Nサロンというブランドを動かしているのは私たち2人が中心なので、プロジェクトにかなり没頭しましたね。
両社とも前例のないプロジェクトですし、まずはスピーディに実践することを目指しました。ランディングページはデザインツールのSTUDIOでシンプルなものを制作し、決済方法としては「有料note※」を立て、チケット代わりに販売することで、すみやかに立ち上げることができました。
バラエティ豊かな登壇者に恵まれたこともあり、幸いにも沢山のお申込みをいただいたのですが、申込者一人ひとりに入金の確認やリマインド、質疑応答や参加可否のやり取りをしたりと、細かい事務作業も多かったですね。
※ noteの記事は、値段を設定して有料販売することも可能
――水野さん一人で全参加者分を対応したのですか?
水野 はい、かなり大変でしたが、私一人でやりました(笑)。その結果よかったのは、コミュニティのメンバーとなる97人を1対1の関係で認識できたことです。
大人数だとついつい一括りにしてコミュニティメンバーを見てしまいがちですが、参加費用も決して気軽に支払える金額ではないですし、サロンを構成するメンバー一人ひとりがどうやったら満足してくれるのか?という点には常に向き合い続けました。

永吉 一般的な企業のコミュニティは何かしら売りたい製品があって、その製品を売ってくれる人たちを集めるような性質がありますよね。
Nサロンは、そうしたコミュニティとは大きく違っていて、コミュニティを継続させて育てていくこと自体を目的化しています。
そのため、メンバーとの向き合い方も違いますよね。1対1でコミュニケーションがとれていますし、イベント後の飲み会にも参加したりする。
水野 実は、最初のころはメンバー同士が雑談できる場所をあえて作らなかったんですよね。
まだ場の空気があったまっていないうちに作って、閑散としているのもいやだなと思っていたので。
当初はスタートして1ヶ月くらい経ったら、交流を促す仕組みをいれようと考えていたのですが、想像以上にメンバー同士が仲良くなるスピードが速く、1ヶ月も経たないうちに「部活を作っていいよ」という提案をしました。
振り返ると、参加者を一律でサロン内のイベントやゼミに参加し放題とした設計が、功を奏したと思います。
実際に、イベントに多く参加するメンバー同士は週に2、3回は顔を合わせていました。これだけの頻度で会う人って、会社の同僚以外にはなかなかいないですよね。
――現在は、いくつ部活があるんですか?
水野 全部で15の部活があります。すべて、私たちが用意したわけではなく、サロンメンバーが自主的に立ち上げたものです。たとえば、新聞部という各自で持ち寄ったニューストピックスについて議論していく部活なんかは人気ですね。
ほかにも、もう少しゆるい感じのチームもあって、飲みに行くために集まる部活やスポーツ系の部活、九州出身者だけが集う部活なんかもあります。
Nサロンの部活の仕組みとしては、われわれ運営はほぼタッチせず、活動の場を提供することがあるくらいで、メンバーの中から立候補をした部長達に運用を任せています。それでも、平日や土日を問わず集まっているようですし、メンバー主体で自走するコミュニティになってきていると感じます。
――メンバーが自走するようになったきっかけや仕組みなどはあったのですか?
永吉 当初から一過性のイベントにしないために、メンバーが自発的に動いてもらうようにすることは意識していましたね。
自走するきっかけになったと思っているのは、「Nサロン未来会議」というゼミ。Nサロンで自分は何を目的にしていて、何をやり遂げたいかを共有する場でした。
そこで議論メシの黒田悠介さんにファシリテートをしてもらって、最後に運営への要望をメンバーから出してもらったんです。そこで出てきたのが「この後どうですかバッジ」という仕組みでした。
このバッジをつけていると、イベント後に飲みに行く気があることを周囲に示すサインとなる、という案だったのですが、そのアイデアが発表された時に場がワッと湧いたんですよね。
水野 あの瞬間に、みんな、飲んで交流したかったんだということが可視化されて、その日からメンバー同士で飲みに行くことが増えました。
永吉 その後は、メンバーの顔と名前が一致しないからメンバーの名簿を作りたいということで、卒業アルバムを作る部活動なんかも生まれました。
水野 Nサロン未来会議は「何のためにあなたたちはNサロンに来てるの?」とそれぞれにスポットをあてる感じがすごくよかった。特に印象的だったのは黒田さんがおっしゃった「一隅を照らす」という話でした。
置かれている立場は異なるのを前提として、それぞれがコミュニティにとって良いと思うことをしよう、という考えで、コミュニティ運営においてはとても重要なことです。
人任せにするのではなく、皆の役に立つことを少しずつ積み重ねていくことで、自分自身も居心地がよくなる。そういった考え方が浸透したきっかけになったと思います。
このように、Nサロンというハコを用意して、サロンメンバーのやりたいことを把握・共有し、動き出せるようなきっかけを設けたことで徐々に自走できるコミュニティへと変化していきました。

――最後に、今後の展望やアドバイスもいただきたいです!
水野 コミュニティをつくる際に、目的を定めずに始めてもあまりいいことはないのですが、社内事情などで、議論しきれずに走ってしまうことって意外と多いですよね。
それがどのような影響をもたらしてくれるかは、企業によって違うので、目的はしっかり決めたほうがいいと思っています。
永吉 オールドメディアと呼ばれている私たち日経が、noteのようなスタートアップ企業と組んでうまくやっていくには、両者のコミュニケーションはもちろんですが、それぞれの社内で合意を取っていくこともすごく重要だと思いますね。
水野 永吉さんだったから、日経さんだったから実現できたコミュニティだと思うんです。
私たちとしては色々なメディアがnoteに場所をもってくださることはウェルカムなので、ぜひ、さまざまなメディアの方とコラボしていきたいです。
水野さん、永吉さんお忙しいところありがとうございました!
【執筆】花岡 郁
【撮影】小澤 健祐
【編集】Engagemate編集部
※本記事に掲載されている取材内容、プロフィール等の情報は、2019年6月6日時点のものです。
※本記事は2019年6月6日に公開されたGrowth Hack Journalの記事を転載したものです。

永吉 貴志(ながよし たかし)

水野 圭輔(みずの けいすけ)
Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。