2025.08.21
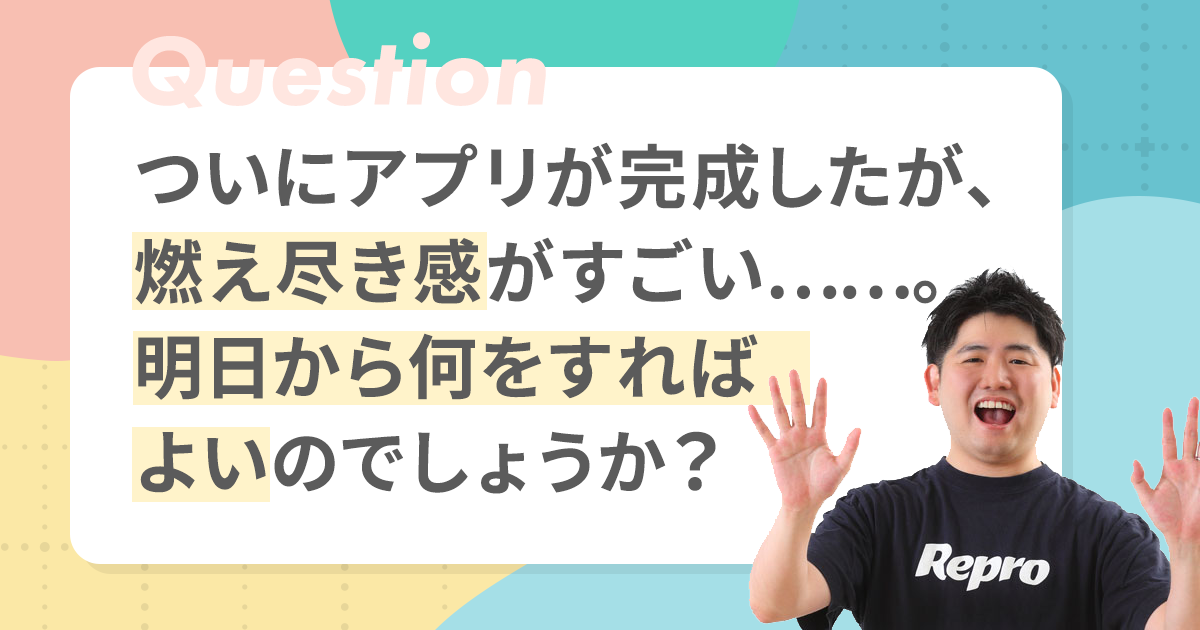

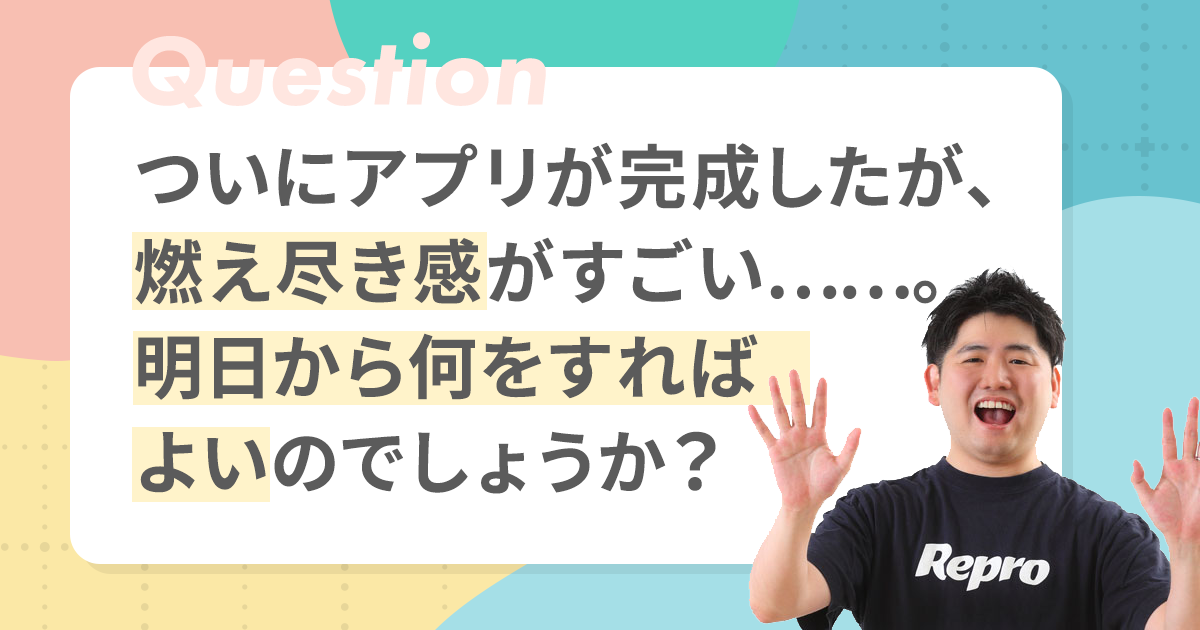
【今回のご相談】
突然ですが、燃え尽きました。約1年かけて私の部署で自社アプリを開発したんです。弊社初のアプリです。先月公開できました。外部パートナーを途中で変更したり、上司の思いつきや社内からのいろんな要望を可能な限り盛り盛りにしたり、なかなか良いシゴトをしたなと自負しています。ですが、燃え尽きたんです。上司はアプリのことを忘れているかもしれません。私は明日から何をすればよいかわかりません(他の業務はあるんですが、アプリはほぼ試合終了です)。
先月までは、「アプリ作るぞ!」って、そのゴールをめがけて突っ走ればよかったじゃないですか。今月から何すればいいんでしたっけ?(メーカー・デジタルマーケティング部門、20代男性)
多くの企業が、デジタル施策の一環としてアプリを導入するようになりました。しかし、「とりあえず作る」ことが目的になってしまい、期待した成果につながっていない、あるいは、作った後で何を目標にすればよいか見失っている、といった声も少なくありません。その背景には、「誰に、何を届けたいのか」が曖昧なまま開発が進み、結果として“使われないアプリ”になってしまうという課題があります。
今回は、アプリの役割を再定義し、運用を見直すための4つの視点をご紹介。現場でよくある課題や成功事例を交えながら、“使われるアプリ”に変えていくためのヒントをお届けします。
アプリ施策は「開発して終わり」ではなく、その後の運用によって成果が大きく変わります。開発に至った背景や目的を見失ったまま運用を続けた場合、使われないアプリになってしまう可能性も……。
まずは、なぜアプリを作るだけでは成果につながらないのか、現場で起こりがちな課題とともに掘り下げていきます。
近年、スマホでのユーザー体験が向上し、機能が充実したアプリも増えています。その影響から、「自社のアプリをもっと多機能にしなければ」と考える企業も多いのではないでしょうか。
しかし、目的がはっきりしないまま機能を次々と追加していくと、ユーザーの利用目的や他チャネルとの使い分けが不明確になり、「結局何のためにこのアプリが存在するのか」がユーザーに伝わらなくなってしまいます。
たとえば、「LINEでもスタンプがもらえる」「Webにも会員情報が載っている」「紙のクーポンもある」といったように、顧客接点が散らばった状態で、さらにアプリに同様の機能を加えてしまうと、ユーザーの混乱を招く原因になってしまいます。
こうした運用を続けていくと、「せっかく時間やコストをかけたのに、成果につながらなかった」という評価になりかねません。

アプリは目的を達成するための「手段」であるはずが、いつの間にか「作ること」がゴールになってしまうことがあります。中には、「とりあえずアプリを作ろう」という判断が先行してしまい、その後の運用や成果に向けた設計が置き去りになっているケースも珍しくありません。
たとえば、「会員証代わりにアプリを活用したい」「スタンプカードや来店ミッションを実装したい」といった社内の要望をもとに、目的が曖昧なまま外注でアプリを開発。しかし、いざリリースしてみると「売り上げに貢献していない」「使われていない」という課題に直面する。こうしたパターンは実際によく見られます。
特にパッケージ型アプリでは、導入後に「思ったようにデータが取れない」「UIが柔軟に変えられない」といった制約に気づき、改善が難航する場合も。だからこそ、アプリ導入の前段階で「自社にとってアプリはどんな役割を果たすのか」を見極めることが重要です。

ユーザーに「アプリを使うメリット」を実感してもらうには、ユーザー体験の軸をしっかりと定めておく必要があります。ここでは、アプリが果たすべき役割を再整理したうえで、使われるアプリに変えるために押さえておきたい4つの視点を紹介します。

まずは、「なぜその体験をアプリで提供するのか」という視点を持つことが大切です。たとえば、会員証の提示やポイントの確認、購買履歴のチェックなどは、アプリで完結するからこそ便利だと感じられる体験です。一方で、Webで十分に代替できる体験であれば、本当にアプリで提供すべき体験なのかを見直す余地があるかもしれません。
常時接続・オフライン対応・プッシュ通知など、アプリならではの特性を活かすことが、ユーザーに「使い続けたい」と思ってもらえる設計につながります。
なかなか成果につながらない場合は、いま一度「アプリでしか提供できない体験とは何か?」という視点に立ち返り、設計を見直すことをおすすめします。
【関連記事】
ユーザーに“リアル”に求められ、課金のきっかけになるモバイルアプリの6つの機能(Repro Journal)
リリースは仕事の50%、アプリの新機能を開発するなら定着にまで責任を持つべき(Repro Journal)
「この機能があると便利そう」「他社もやっているから真似したい」など、アプリの企画段階では、つい“やりたいこと”や“できること”から発想しがちです。
しかし、重要なのは「なぜその機能を実装するのか」「その機能でユーザーにどんな価値を届けたいのか」という視点です。
たとえば、スタンプカード機能をつけるとしても、「継続利用を促したい」「来店のきっかけをつくりたい」といった目的があってこそ、効果的な設計になります。実際に、Reproの支援先でも、「ユーザーにとっての意味」を軸にクーポンやポイント施策を見直したことで、CV率やリピート率が改善した事例があります。
このように、アプリでやるべきことを絞りこむ際には、「何ができるか」ではなく「何を届けたいか」という視点から設計を見直すことが大切です。
どれだけ丁寧に体験を設計しても、UIや導線が使いづらければ、ユーザーにその価値は伝わりません。
ユーザーがよくアクセスする画面と、実現したいKPI(会員登録・購入・クーポン利用など)につながる画面の導線がしっかり接続されているか。ユーザーの行動を妨げるような、わかりづらい導線になっていないか。そうした点をひとつずつ見直すことで、ユーザーに対して価値を届けることができ、成果にもつながりやすくなります。
なお、アプリの導線は、一度設計したら終わりではありません。ログやヒートマップなどを活用しながら、実際のユーザー行動をもとに継続的に改善に取り組んでいきましょう。
【関連記事】
UI/UXに関する最新記事(Repro Journal)
アプリを“使われるチャネル”として育てていくためには、アプリ単体での最適化にとどまらず、タッチポイント全体のなかで「アプリがどんな役割を担うべきか」を明確にしておくことが不可欠です。
たとえば、「店舗での会員登録→アプリのインストール→クーポン利用」といった自然な導線を設計することで、ユーザーにとってのストレスを減らし、活用のハードルを下げられます。
また、プッシュ通知をオフにしている人にはメールでフォローするなど、他チャネルとうまく連携することで、ユーザー体験に一貫性が生まれます。“アプリでやるべきこと”を見極めるには、こうした全体設計の視点が欠かせません。チャネル全体の中でアプリが担うべき価値を明確にし、その強みを活かした体験設計へと磨き上げていきましょう。
顧客接点が多様化する今、「アプリが担うべき役割を明確にすること」はますます重要になっています。あれもこれも詰め込むのではなく、「アプリだからこそ提供すべき体験」に絞り込むこと。それが、ユーザーに選ばれるアプリへの近道になります。
届けたい価値から逆算して必要な機能やUIを選び抜き、他チャネルとの役割分担までを視野に入れた設計を行う。このような視点からアプリを見直すことで、“使われるアプリ”へと着実に近づけるはずです。
Reproでは、アプリの体験設計から施策実行までを一貫して支援しています。課題感が言語化できていない段階でも、お気軽にご相談ください。
▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。
ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。